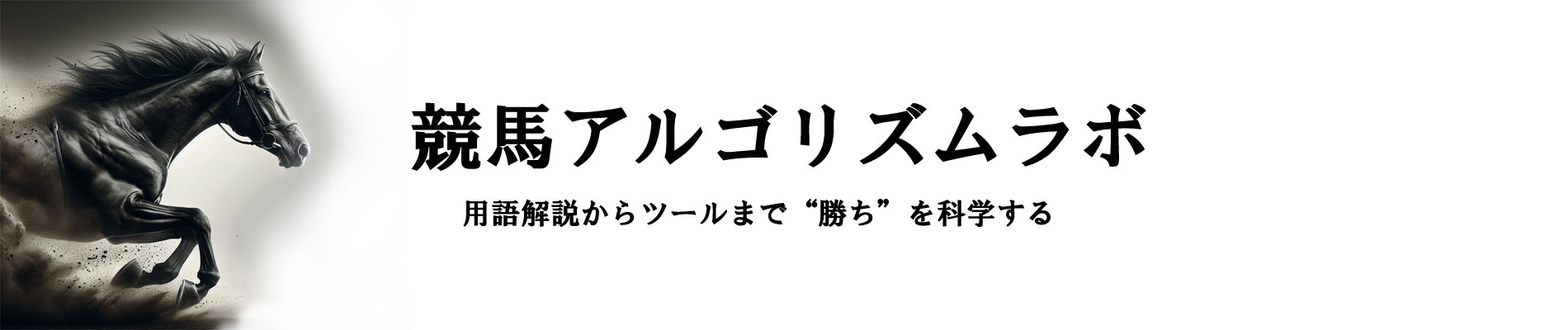競馬中継を見ていると、解説者が「この馬、かかっていますね」と口にすることがあります。「かかる」とは一体どういう意味で、レースにとって良いことなのか、悪いことなのか?そんな疑問を抱いた競馬ファンの方も多いのではないでしょうか。
競馬における「かかる」という言葉は、レースの勝敗を左右するとても重要な要素です。これは、馬がレース中に過度に興奮してしまい、鞍上にいる騎手のコントロールが効かずに前へ前へと暴走気味になってしまう状態を指します。この状態になると、本来ゴールまで温存すべきスタミナをスタート直後から無駄遣いしてしまい、最後の直線で失速して順位を落とす…といった結果に繋がることが非常に多いのです。
この記事では、「競馬のかかるとは何か?」という基本的な意味から、馬がかかる原因、レースへの具体的な影響、そしてパドックやレース映像での見分け方まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。さらに、騎手が馬を制御する技術や、かかり癖をデータとして競馬予想や賭けにどう活かすかという、一歩進んだ視点もご紹介します。この記事を読めば、あなたもレースを見る目が変わり、競馬ファンとしてさらに深く勝負の世界を楽しめるようになるでしょう。
記事のポイント
- 「かかる」という競馬用語の正確な意味とレースへの致命的な影響
- パドックやレース映像から「かかる」馬を見抜く具体的なサイン
- 「かかり癖」をデータとして分析し競馬予想に活かす方法
- 騎手の技術や調教による「かかり癖」の改善アプローチ
競馬の「かかる」とは?意味とレースへの影響を解説

- 「かかる」とは?騎手の制御が効かない馬の興奮状態
- なぜ馬はかかる?3つの原因とかかりやすい馬の特徴
- レースへの致命的影響。スタミナ消耗と大敗リスク
- 「折り合い」「引っかかる」との違い。用語を正しく理解
- 初心者必見!競馬中継で「かかる」を見抜くポイント
「かかる」とは?騎手の制御が効かない馬の興奮状態
競馬中継を見ていると、解説者やアナウンサーが「この馬、かかってますね」や「少し行きたがっています」といった言葉を口にすることがあります。競馬を始めたばかりの方にとっては、この「かかる」という言葉が何を意味しているのか、そしてそれがレースにとって良いことなのか悪いことなのか、判断がつきにくいかもしれません。結論から申し上げますと、競馬における「かかる」とは、馬がレース中に過度に興奮してしまい、鞍上にいる騎手のコントロール、つまり指示や制御が効かずに前へ前へと突進しようとする状態を指します。これは多くの場合、レース結果に対してネガティブな影響を及ぼす現象として知られています。
その理由として、競走馬が持つスタミナには限りがある点が挙げられます。特に競馬のレースは、数百メートルを走る短距離戦から、3000メートルを超える長距離戦まで様々です。どの距離であっても、ゴールまで最高のパフォーマンスを発揮するためには、道中での適切なペース配分が不可欠となります。マラソンランナーが42.195キロを走り切るために、序盤はペースを抑え、体力を温存しながら走り、勝負所でスパートをかけるのと同じ理屈です。騎手はレース全体の流れを読み、自分の馬の能力を最大限に引き出すためのペースを頭の中に描いています。スタート直後から中盤にかけては、あえて馬を抑えてリラックスさせ、力を溜めさせる「折り合い」を重視します。しかし、馬がかかってしまうと、この騎手の描いたレースプランが根本から崩れてしまいます。馬が騎手の意に反して暴走気味にスピードを上げてしまうため、本来は温存しておくべきスタミナをレースの序盤で無駄に消費してしまうのです。
具体例を挙げると、18頭立てのレースで、ある馬が10番手あたりでじっくり脚を溜める作戦を立てていたとします。しかし、スタート直後にゲートが開いた瞬間から馬が興奮し、他の馬を追い抜いて先頭に立とうと必死になってしまう。騎手は手綱を強く引いて必死に馬をなだめようとしますが、馬は首を上下に激しく振って抵抗し、騎手の制御を振り切ってハイスピードで走り続けてしまう。これが「かかる」状態の典型的な光景です。こうなると、レースの後半、特に最後の直線という最も重要な勝負どころで、すでにスタミナを使い果たしてしまっているため、他の馬がスパートをかける中で失速して後方へ沈んでいく、という結果に繋がることが非常に多いのです。特に、スタミナが勝敗を大きく左右する長距離レースにおいて、「かかる」ことは致命的な欠点となり得ます。
この「かかる」という状態は、JRA(日本中央競馬会)の公式な競馬用語では「折り合いを欠く」と表現されます。「折り合い」とは、騎手と馬の呼吸がぴったりと合致している状態を指す言葉であり、人馬一体となってスムーズに走れていることを意味します。つまり、「かかる」はその正反対の状態で、騎手と馬の意思疎通がうまくいかず、ちぐはぐな走りになっていることを示しているのです。馬は非常に繊細で、闘争心が強い動物です。他の馬が近くにいたり、大観衆の声援を浴びたりすることで興奮状態に陥りやすい性質を持っています。この興奮をいかにコントロールし、馬をリラックスさせてレースに集中させるかが騎手の腕の見せ所の一つでもあります。したがって、「かかる」という現象は、単に馬の気性の問題だけでなく、騎手の技術や馬との相性も深く関わってくる、非常に奥が深い要素なのです。競馬の予想や観戦において、この「かかる」という状態を見抜けるようになると、レースの展開予測や馬券の検討がより一層深みを増し、競馬の面白さをさらに感じられるようになるでしょう。
なぜ馬はかかる?3つの原因とかかりやすい馬の特徴
馬がレース中に「かかる」現象は、単一の原因で発生するわけではなく、複数の要素が複雑に絡み合って引き起こされます。結論として、その原因は大きく分けて「馬自身の気性や性格」「レース展開や騎手との相性といった外的要因」「血統や体調などの背景的要因」という3つのカテゴリーに分類することができます。これらの要因を理解することは、レースの展開を予測し、馬券を検討する上で極めて重要な視点となります。
まず第一に、「馬自身の気性や性格」が最も根本的な原因として挙げられます。競走馬はサラブレッドという品種であり、その根底には極めて強い闘争心と繊細な神経が宿っています。特に、若駒(2歳~3歳前半の馬)は人間で言えば思春期の若者のようなもので、精神的にまだ未熟です。そのため、レースという非日常的な興奮状態に置かれると、冷静さを失いやすい傾向があります。大観衆の歓声、隣を走るライバル馬の存在、ゲートが開く瞬間の緊張感など、あらゆるものが刺激となり、闘争本能が過剰に燃え上がってしまうのです。また、元来臆病な性格の馬が、周囲の状況に恐怖を感じてパニックになり、その場から逃げ出そうとして制御不能なスピードで走ってしまうケースも「かかる」の一種と言えます。このように、馬が本来持っている前向きすぎる性格や、逆に神経質で臆病な性格が、レースという極限状況下で暴走という形で表出することが、かかる最大の理由の一つです。
次に、「レース展開や騎手との相性といった外的要因」も、かかる引き金として非常に大きな役割を果たします。例えば、レース全体のペースが極端に遅い「スローペース」になった場合を考えてみましょう。本来、ある程度のスピードでリズミカルに走りたい馬にとって、スローペースは非常にストレスが溜まる状況です。前に進みたいのに騎手に抑えつけられるため、フラストレーションが募り、騎手の制御に反発して無理やり前に進もうとしてしまいます。これが「かかり」に繋がる典型的なパターンです。また、騎手との相性、いわゆる「折り合い」も無視できません。馬は非常に敏感な動物であり、騎手のわずかな体重移動や手綱越しのコンタクトを敏感に感じ取ります。騎手の乗り方が馬の好むリズムと合わなかったり、騎手が焦って力ずくで馬を抑えようとしたりすると、馬は反発してさらに行きたがってしまいます。人馬の信頼関係が築けていない場合や、その日のコンタクトがうまくいかない場合、馬は騎手をパートナーとして認めず、自分の本能のままに走ろうとしてしまうのです。
そして第三の要因として、「血統や体調などの背景的要因」が存在します。競馬はブラッドスポーツと呼ばれるように、血統が能力や気性に与える影響は絶大です。父馬(種牡馬)や母馬から、気性の激しさや前向きすぎる性格が遺伝することは珍しくありません。特定の血統を持つ馬は、代々「かかりやすい」という評価が定着していることもあり、予想の段階からそのリスクを織り込む必要があります。例えば、父が短距離で圧倒的なスピードを誇った馬は、その産駒もスピード能力を受け継ぐ一方で、気性が前向きすぎて距離が長いレースではスタミナを温存できない、といったケースは頻繁に見られます。さらに、その日の馬の体調も大きく影響します。調教によって十分にガス抜きができておらず、有り余るエネルギーを持て余している状態の馬は、レースでそのエネルギーを発散させようと暴走しがちです。パドック(レース前に馬が周回する場所)で異常に汗をかいていたり、落ち着きなく歩き回っていたりするのは、過度の入れ込みや興奮のサインであり、「かかる」前兆と捉えることができます。これらの3つの要因は独立しているわけではなく、相互に影響し合っています。例えば、「気性が激しい血統の若駒が、スローペースのレースで経験の浅い騎手とコンビを組む」といった状況は、かかるリスクが非常に高い典型例と言えるでしょう。
レースへの致命的影響。スタミナ消耗と大敗リスク
競馬において馬が「かかる」という状態は、単に見た目の走りがぎこちないというレベルの問題ではなく、レース結果そのものに致命的な影響を及ぼす極めて深刻な現象です。結論から申し上げると、かかることは馬が持つ貴重なスタミナをレースの序盤で意図せず大量に消耗させることに直結し、その結果として大敗につながるリスクを飛躍的に高めます。たとえその馬がどれほど優れたスピード能力や潜在能力を秘めていたとしても、このスタミナの無駄遣いという大きなハンディキャップを背負って勝利を収めることは、ほとんど不可能と言っても過言ではありません。
その理由は、競走馬のエネルギー消費の仕組みと、レースにおけるペース配分の重要性にあります。競馬のレースとは、本質的に、馬が体内に蓄えている限られたエネルギー、すなわちスタミナを、いかに効率良くゴールまでの道のりで配分するかを競うスポーツです。騎手は、馬を精神的にリラックスさせ、可能な限り酸素を効率的に体内に取り込みながら走る「有酸素運動」の状態で道中を進ませることを目指します。この状態であれば、エネルギー消費は比較的緩やかで、勝負どころである最後の直線に向けて十分なスタミナを温存することができます。しかし、かかっている状態の馬は、これとは全く逆の状況に陥っています。騎手の制御に抵抗して常に前に進もうと力んでいるため、首や肩、背中といった全身の筋肉が硬直し、呼吸も浅く、乱れがちになります。これはエネルギー効率が著しく悪い「無酸素運動」に近い走り方であり、体内に蓄えられたスタミナの源であるグリコーゲンを、まるで湯水のように急激に消費してしまうのです。同時に、疲労の原因となる乳酸などの疲労物質が体内に早期から蓄積され始め、筋肉のパフォーマンスを著しく低下させます。これは、マラソン選手がスタート直後から全力疾走をすれば、レース中盤に差し掛かる前に必ず失速してしまうのと同じ原理です。かかってしまった馬は、レースのクライマックスである最後の直線に入るはるか手前で、すでにエネルギー切れ、つまりガス欠の状態に陥ってしまうのです。
具体的な例を挙げてみましょう。例えば、2400メートルのジャパンカップや、3200メートルにも及ぶ天皇賞(春)のような長距離レースを想像してみてください。これらのレースでは、ゴールまでの長い道のりを見据えて、道中でいかに馬をリラックスさせ、力を温存できるかが勝敗を分ける最大の鍵となります。もし、スタートからわずか1000メートルの区間をかかり通しで走ってしまった馬がいたとしたら、その馬は残りの長い距離を走り切るためのエネルギーをほとんど残していません。レースが動き出す後半、他のライバルたちが満を持してスパートを開始する中、その馬はまるでエンジンが停止したかのようにズルズルと後退していくことになります。ファンからの大きな期待を背負った人気馬が、信じられないような大差で負けるという光景が時折見られますが、その多くはこの「かかり」が原因です。また、1600メートルのマイル戦のような比較的短い距離のレースであっても、その影響は甚大です。スタミナよりも純粋なスピード能力の比重が高まる距離ではありますが、それでもレースを通じたペース配分は不可欠です。かかってしまった馬が意図せずハイペースを作り出してしまうと、レース全体の展開にも波乱を呼びます。その馬自身が終盤に失速するのはもちろんのこと、その馬をマークしていた他の先行馬までが予定外の速いペースに巻き込まれ、共倒れになってしまうケースも少なくありません。その結果、本来であれば展開の助けが必要な後方待機組、いわゆる「差し・追い込み馬」が、先行集団が総崩れになったところをまとめて交わし去るという、波乱の決着を生む原因にもなるのです。つまり、たった一頭のかかった馬が、レース全体の力関係や展開を根底から覆してしまう可能性すら秘めているのです。このように、馬がかかることは、単に騎手の指示に従わないという表面的な問題ではありません。それは、レースという競技の根幹をなす「スタミナ配分」という大戦略を、スタート直後に自ら放棄してしまう行為に他ならないのです。騎手がどれほど完璧なレースプランを描いていようとも、パートナーである馬がかかってしまえば、その全ては水の泡と帰します。したがって、競馬を予想する上で、各馬のかかるリスクを事前に見極めることは、大きな勝利を掴むためだけでなく、予期せぬ大敗を避けるための重要な危機管理能力と言えるでしょう。
「折り合い」「引っかかる」との違い。用語を正しく理解
競馬の世界には、専門的な用語が数多く存在します。その中でも、「かかる」という言葉の周辺には、「折り合い」や「引っかかる」といった、似ているようでいて実はニュアンスの異なる表現がいくつかあります。これらの言葉を正確に理解することは、競馬中継の解説を深く味わい、レースの状況を的確に把握するために非常に重要です。結論として、「かかる」は騎手の制御が効かない興奮状態を指すのに対し、「折り合い」はその正反対の理想的な状態を、「引っかかる」は「かかる」とほぼ同義ですが、より瞬間的、物理的な抵抗のニュアンスを含むことが多い言葉です。これらの違いを理解することで、人馬の関係性やレース中の機微をより鮮明にイメージできるようになります。
まず、最も対照的な関係にあるのが「かかる」と「折り合い」です。前述の通り、「かかる」は馬が騎手の意に反して前へ前へと行きたがり、スタミナを無駄に消費しているネガティブな状態を指します。これに対して、「折り合いがついている」または単に「折り合っている」という状態は、競馬における人馬一体の理想形を表現する言葉です。これは、馬が精神的にリラックスしており、騎手の扶助(ふじょ)、つまり手綱や脚、体重移動による微細な指示に素直に従い、求められたペースでスムーズに走れている状態を意味します。騎手と馬の呼吸がぴったりと合っているため、エネルギーのロスが最小限に抑えられ、勝負どころに向けて万全の態勢で力を溜めることができています。マラソンランナーが集団の中でリラックスして走り、呼吸を整えている姿を想像すると分かりやすいでしょう。レース中継で解説者が「この馬はうまく折り合っていますね」とコメントした場合、それはその馬と騎手が完璧なコミュニケーションを築けており、レースプラン通りに運べているという最高の賛辞なのです。つまり、「かかる」が制御不能な「不協和音」であるとすれば、「折り合い」は調和のとれた「ハーモニー」と言えるでしょう。
次に、「かかる」と「引っかかる」の違いについて考えてみましょう。この二つの言葉は、ほとんど同じ意味で使われることが多く、明確な定義の境界線があるわけではありません。どちらも馬が騎手の制御に反して行きたがる状態を指す点では共通しています。しかし、そのニュアンスには微妙な差異が存在します。「かかる」という言葉が、レースの序盤から中盤にかけて持続的に馬が興奮し、冷静さを欠いている精神的な状態全体を指すことが多いのに対し、「引っかかる」は、より物理的、瞬間的な抵抗の側面を強調する際に使われる傾向があります。具体的には、騎手が手綱を引いて馬を抑えようとした際に、馬がハミ(口にくわえさせる馬具)を強く噛んでグイグイと前に引っ張っていくような、物理的な抵抗の強さを表現する際に「引っかかる」という言葉が選ばれやすいです。例えば、「コーナーでペースが落ちた瞬間にグッと引っかかってしまった」というように、特定の場面での突発的な抵抗に対して使われることがあります。一方で、「この馬は気性的に気負いすぎて、スタートからずっとかかり通しだった」というように、「かかる」はレース全体を通しての精神的な高ぶりを表すのにより適しています。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、実況や解説の中ではほぼ同義語として扱われるのが実情です。重要なのは、どちらの言葉が使われても、「馬が騎手の意図以上に前に行こうとしており、スタミナをロスしている危険なサインである」という本質的な意味を理解しておくことです。
これらの用語を正しく使い分けることで、レースの解像度は格段に上がります。例えば、レース序盤で「〇〇番、少し行きたがっていますが、鞍上がうまくなだめて、なんとか折り合いをつけました」という実況があれば、それは「かかりかけたが、騎手の技術によって未然に防がれた」という一連の攻防があったことを意味します。また、「最終コーナーで前の馬に並びかけようとしたときに一瞬引っかかりましたが、すぐに修正しました」という解説からは、勝負どころでの一瞬の力みを騎手が見事にコントロールしたという、プロフェッショナルな技術が垣間見えます。このように、「かかる」「折り合い」「引っかかる」という言葉は、単なる状態を表すだけでなく、その裏側にある騎手と馬との間の絶え間ないコミュニケーションや、レース中のミクロな駆け引きを映し出す鏡のような役割を果たしているのです。これらの言葉の意味を深く理解すればするほど、競馬というスポーツの奥深さと、人馬が織りなすドラマをより一層楽しむことができるようになるでしょう。
初心者必見!競馬中継で「かかる」を見抜くポイント
競馬のレース観戦に慣れていない初心者の方にとって、レース中に展開される複雑な駆け引きや、一頭一頭の馬の状態を瞬時に把握するのは至難の業かもしれません。しかし、レースの勝敗を大きく左右する「かかる」という現象は、いくつかの特定のポイントに注目することで、初心者の方でも見抜くことが可能です。結論として、競馬中継の映像の中から「かかる」馬を発見するためには、主に「騎手の動き」「馬自身の動きや様子」「実況・解説の言葉」という三つの要素を注意深く観察することが極めて有効な方法となります。これらのサインは、馬が騎手のコントロールから外れかけていることを示す、分かりやすい警告信号なのです。
まず最も視覚的に捉えやすいのが、「騎手の動き」です。リラックスして馬と折り合っている騎手は、上半身をやや前に傾け、馬の動きに合わせてリズミカルに体を動かしています。腕や手綱にも適度な遊びがあり、力みが見られません。一方、馬がかかってしまった場合、騎手の姿は一変します。馬が前へ前へと突進しようとするのを必死で抑え込むため、騎手は上半身を後ろに反らせるような体勢になり、全体重をかけて馬を制御しようとします。腕はピンと伸びきり、手綱を握る拳はグッと後ろに引かれ、まるで綱引きをしているかのような見た目になります。テレビの画面越しでも、その必死さが伝わってくるはずです。さらに細かい動きとして、騎手が手綱を交互に小刻みに動かしたり、馬の首筋をポンポンと優しく叩いたりする仕草が見られることがあります。これらは、興奮している馬をなだめ、なんとか落ち着かせようとするための騎手の工夫です。このような騎手の通常とは異なる力強いアクションや、馬をなだめるような仕草が見られたら、その馬はかかっている、あるいはかかりかけている可能性が非常に高いと判断できるでしょう。
次に注目すべきは、「馬自身の動きや様子」です。騎手の制御に抵抗している馬は、その動きにも特徴的なサインが現れます。最も分かりやすいのが、首の動きです。騎手が手綱を引いて抑えようとする力に反発して、馬は首を激しく上下に振ることがあります。これは、人間が嫌なことから逃れようとして首を振るのと似たような、明確な抵抗の意思表示です。また、横から馬の顔がアップで映し出された際には、口元にも注目してみてください。「口を割る」と表現されますが、ハミ(口にくわえさせた金属製の馬具)への抵抗から口が不自然に開き、歯が見えている状態になることがあります。これも、騎手の制御を受け入れたくないというサインの一つです。走り方自体も、スムーズさを欠き、どこか力んでバタバタと不器用なフォームに見えることがあります。他の馬がリラックスして滑らかに走っているのに対し、かかっている馬は明らかに周囲とのリズムが合わず、ちぐはぐな印象を与えます。特に、集団の中で走っているにもかかわらず、前の馬との距離を異常に詰めてしまったり、外側に持ち出してでも前に出ようとしたりする動きは、かかっている典型的な兆候と言えます。
そして最後に、レース観戦における最大の味方となるのが、「実況アナウンサーや解説者の言葉」です。彼らは長年の経験を持つプロフェッショナルであり、レース中の馬の細かな変化を瞬時に見抜き、言葉で伝えてくれます。「〇〇番、かかっていますね」「これは少し行きたがっています」「鞍上、必死になだめていますが、折り合いを欠いています」といった直接的な表現が聞こえてきたら、それは間違いなくその馬がかかっている証拠です。画面に映っている該当馬の様子を、先に述べた騎手や馬の動きのポイントと照らし合わせながら確認してみると、理解がより一層深まります。また、「もう少しリラックスしたいところですね」「前の馬を壁にして落ち着かせたい」といった間接的な表現も、かかり気味であることを示唆する重要なヒントです。一つ注意したいのは、「逃げ馬」との違いです。先頭を走っている馬がすべてかかっているわけではありません。作戦として意図的に先頭に立ち、レースを引っ張っている「逃げ馬」は、騎手の制御下でリラックスして走っています。しかし、かかってしまった結果、意図せず先頭に立ってしまった馬は、騎手が必死に抑えようとしている様子が見て取れるはずです。この違いを見極める上でも、騎手の動きや実況の言葉が大きな助けとなります。これらの三つのポイントを意識して競馬中継を見る習慣をつければ、これまで何となく眺めていたレースの光景が、人馬の駆け引きに満ちたドラマとして、より鮮明に、そして面白く見えてくるはずです。
競馬予想が変わる「かかる」の見抜き方と騎手の技術

- パドックと返し馬で見抜く!かかる馬の視覚的サイン
- 騎手の腕の見せ所!馬を抑える技術とポジション取り
- 予想が変わる!データで見る「かかり癖」と馬券戦略
- かかり癖は治る?トレーニングと騎手の調教法
- 【比較表】かかりやすい馬 vs 折り合える馬の特徴
パドックと返し馬で見抜く!かかる馬の視覚的サイン
競馬予想のファクターは、過去のレース成績や血統、調教タイムなど多岐にわたりますが、それらのデータと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、レース直前の馬の「生の状態」を見極めることです。そのための絶好の機会となるのが、レース発送前にファンに馬の姿をお披露目する「パドック」と、その後に本馬場に入ってから行われる「返し馬」と呼ばれるウォーミングアップです。結論から言えば、この二つの場面で馬が見せる特定の視覚的サインを注意深く観察することで、その馬がその日のレースで「かかる」リスクをどの程度抱えているかを、高い精度で予測することが可能になります。これらのサインは、馬の精神状態を映し出す鏡であり、百のデータよりも雄弁にその日のコンディションを物語ることがあるのです。
まず、レース前の最も重要な観察の場であるパドックについて詳しく見ていきましょう。パドックでは、出走馬が厩務員に引かれて周回します。ここで注目すべき最大のポイントは、馬の「入れ込み」具合です。入れ込みとは、レースを前にして馬が過度に興奮し、冷静さを失っている状態を指し、これがレース本番での「かかり」に直結するケースが非常に多いです。その最も分かりやすいサインが「汗」です。もちろん、暑い夏の日であればどの馬もある程度汗をかくのは自然なことです。しかし、季節や気温に関係なく、首筋や肩、両方の後ろ脚の間といった部分に、びっしょりと玉のような汗をかいている馬は要注意です。特に、その汗が白く泡立っている場合は、極度の興奮状態にあることを示す危険な兆候とされています。これは、有り余るエネルギーが内側から燃え上がっている証拠であり、ゲートが開いた瞬間にそのエネルギーが暴走する形で発散される可能性を強く示唆しています。
汗と並行して観察したいのが、馬の「歩様」と「態度」です。落ち着いている馬は、リラックスしてゆったりと、それでいて力強い足取りで周回します。一方、入れ込んでいる馬は、終始落ち着きがなく、小刻みに足踏みをする「チャカチャカ」とした歩き方を見せることがあります。また、首を不自然に高く上げ、周囲をキョロキョロと見回して警戒心をむき出しにしたり、厩務員が引く手を無視してグイグイと前に進もうとしたりするのも、精神的に高ぶりすぎているサインです。中には、他の馬に噛みつこうと威嚇したり、嘶き(いななき)を連発したりする馬もいます。これらの行動はすべて、闘争心が空回りして冷静さを失っていることの現れであり、かかるリスクが非常に高い状態と言えます。
パドックでの観察を終えた後、次に注目するのが、騎手が騎乗して本馬場に入場してからの「返し馬」です。これは、レース前の最終ウォーミングアップであり、馬の走りそのものを直接確認できる貴重な機会です。ここでも、かかるリスクを判断するための重要なサインがいくつも現れます。最も注目すべきは、騎手と馬とのコンタクト、すなわち「折り合い」です。騎手が馬場に入った途端、馬が猛然と走り出してしまい、騎手が必死に手綱を絞って抑え込んでいる光景が見られたら、それはもはや赤信号です。これは、パドックでの興奮状態が全く収まっていないことを意味し、レース本番でもかかることがほぼ確実視されます。理想的な返し馬は、騎手の指示通りに軽やかなキャンター(駆け足)で走り、いつでもストップできる制御された状態です。しかし、かかり気味の馬は首を高く上げてしまい、騎手の制御に反発して前のめりな走りになります。他の馬がリラックスして走っている中で、一頭だけ明らかに速いスピードで走ってしまっている場合も、同様に危険なサインです。返し馬はあくまでウォーミングアップであり、ここで無駄な体力を使うことは、本番でのスタミナ切れに直結します。このように、パドックでの精神状態の観察と、返し馬での走り方の確認という二段階のチェックを行うことで、その日の馬が抱える「かかる」リスクを立体的に評価することができます。これらの視覚的サインを読み解く力は、一朝一夕に身につくものではありませんが、意識して観察を続けることで、必ずやあなたの競馬予想の精度を格段に向上させる強力な武器となるでしょう。
騎手の腕の見せ所!馬を抑える技術とポジション取り
馬がレース中に「かかる」という現象は、馬自身の気性や体調が大きな要因であることは間違いありません。しかし、それをレース中にコントロールし、馬の能力を最大限に引き出すことができるかどうかは、ひとえに鞍上にいる騎手の技術にかかっています。結論として、かかる馬を御する騎手の能力は、単なる腕力ではなく、馬との対話を可能にする繊細な技術と、レース展開を読む戦略的なポジショニングの二つの側面から成り立っています。これらはまさに「騎手の腕の見せ所」であり、一流のジョッキーがなぜ一流たり得るのかを示す、最も分かりやすい指標の一つと言えるでしょう。
まず、馬を抑える「繊細な技術」について考えてみましょう。馬がかかって前に進もうとするとき、初心者であれば力ずくで手綱を後ろに引っ張ってしまうことを想像するかもしれません。しかし、これは多くの場合、逆効果です。馬は口に装着されたハミ(金属製の馬具)を通じて騎手の意思を感じ取りますが、強く引かれすぎると痛みや不快感からパニックに陥り、さらに強く反発しようとします。これでは、馬との対話ではなく、単なる力と力の衝突になってしまい、問題は解決しません。一流の騎手が行うのは、このような強引な制御ではなく、あくまで馬とのコミュニケーションを試みる、非常にデリケートな扶助(ふじょ)です。例えば、手綱を常に強く張るのではなく、リズミカルに引いたり緩めたりを繰り返すことで、馬に「落ち着け、まだ行くときではない」と優しく語りかけます。また、左右の拳を交互にわずかに動かすことで、馬の意識を前に向けることからそらし、集中力をコントロールしようとします。さらに、手綱だけでなく、自身の体重移動や脚(きゃく)による合図も駆使します。馬の首筋を優しく撫でてリラックスを促したり、馬体を脚で軽く圧迫してバランスを整えたりと、全身を使って馬との調和を図ろうとします。最も重要なのは、騎手自身が冷静さを保つことです。馬は騎手の緊張を敏感に察知するため、騎手が焦れば焦るほど、その不安が馬に伝播し、悪循環に陥ってしまいます。どのような状況でも冷静沈着に、馬に対して「信頼できるリーダー」として振る舞うことができる精神的な強さこそが、かかる馬をなだめるための根幹をなす技術なのです。
次に、同じく極めて重要な要素である「戦略的なポジション取り」についてです。馬は周囲の環境に大きく影響される動物です。特に、目の前に広々とした空間があったり、すぐ隣で他の馬が競り合っていたりすると、闘争本能が刺激されて興奮しやすくなります。熟練の騎手は、この馬の習性を深く理解しており、レース中の位置取り、すなわちポジションを巧みに利用して馬の精神状態をコントロールします。その最も代表的な技術が、「壁を作る」というものです。これは、かかりそうな馬を、意図的に他の馬のすぐ後ろにつけることで、物理的・心理的な「壁」として利用する戦術です。前の馬の存在が自馬の視界を遮り、前に行きたいという気持ちを削ぐ効果があります。また、前の馬がペースメーカーの役割を果たすため、自然とそれに合わせたペースで走ることになり、無理な暴走を防ぐことができます。レース中継で、ある馬が他の馬群の中にスッポリと収まって走っている光景を見たことがあるかもしれませんが、あれは騎手が意図的に「馬群を壁にして」馬を落ち着かせている場面なのです。
逆に、やってはいけないのが、かかりそうな馬を連れて、周囲に他の馬がいない外々を走らせることです。これは、馬の前に遮るものが何もなく、闘争本能を煽るだけの無防備な状態であり、かかるリスクを最大化させてしまいます。どの枠からスタートし、レース序盤でどの馬の後ろにつけるか。レース全体のペースが遅くなりそうだと判断したときに、どのタイミングで少し前にポジションを上げるか。これらすべての判断が、馬をかからせないための戦略的なポジショニングに含まれています。例えば、気性の激しい若駒に経験豊富なベテラン騎手が騎乗した際、たとえ大外枠という不利な条件からでも、巧みに馬を内側の馬群に誘導し、完璧に折り合いをつけて勝利に導くことがあります。これはまさに、騎手の技術と戦略が見事に結実した瞬間であり、競馬の醍醐味の一つです。このように、騎手の仕事は、ただ馬に乗ってゴールを目指すだけではありません。馬という繊細なパートナーの心理を読み解き、持てる技術と知略のすべてを尽くしてその能力を100%引き出す、非常に高度で知的なスポーツなのです。
予想が変わる!データで見る「かかり癖」と馬券戦略
これまでの解説で、馬が「かかる」という現象がレースにいかに致命的な影響を及ぼすかをご理解いただけたかと思います。しかし、競馬の予想、特に馬券の購入という観点から見ると、この「かかる」という要素は、単なるマイナスファクターとして切り捨てるべきものではありません。結論として、「かかり癖」という一見ネガティブに見える特性を、データに基づいて正確に評価し、それを自身の馬券戦略に組み込むことで、危険な人気馬を見抜いて無駄な馬券購入を避けたり、逆に思わぬ高配当を的中させたりする絶好の機会を生み出すことが可能になります。かかり癖は、レースの展開を読み解くための重要な鍵であり、予想の精度を飛躍的に向上させる強力な武器となり得るのです。
その最大の理由は、かかり癖がレースの結果に直接的な影響を与える予測可能なリスクであるためです。そして、そのリスクの兆候は、過去のデータの中に明確な形で記録されています。まず、最も信頼性の高いデータソースは「過去のレース映像」です。JRA(日本中央競馬会)の公式サイトなどでは、過去の全レースの映像を無料で視聴することができます。気になる馬がいれば、その馬の過去数戦のレース映像を必ずチェックする習慣をつけましょう。注目すべきは、レースの序盤から中盤にかけての走りです。騎手が必死に手綱を抑えている様子はないか、馬が首を上下に振って抵抗していないか、馬群の中で落ち着きをなくしていないか、といった視覚的な情報を直接確認することが、何よりも確実な判断材料となります。
映像を見る時間がない場合は、「レース後のコメント」や「ラップタイム」といったテキストデータや数値データが非常に役立ちます。競馬新聞や競馬情報サイトには、レース後に関係者(騎手や調教師)が語ったコメントが掲載されています。ここに「スタートからかかってしまった」「道中ずっと力んで走っていた」「折り合いを欠いてスタミナをロスした」といった直接的な言葉が残っていれば、それはその馬がかかり癖を抱えている有力な証拠となります。また、ラップタイムの分析も有効です。例えば、レース全体のペースが1000m通過62秒という非常に遅い「スローペース」だったにもかかわらず、ある一頭だけが序盤で前のめりに走り、その馬自身の通過タイムが本来の能力以上に速くなっている場合、それはかかって暴走していた可能性を強く示唆します。これらのデータを地道に収集し、馬ごとに「かかりやすさレベル」を自分なりに評価していくことで、予想の精度は格段に向上します。
これらのデータ分析から得られた「かかり癖」という情報を、具体的な馬券戦略に昇華させるには、いくつかの思考パターンがあります。まず一つ目は、「リスク回避」の戦略です。これは、かかり癖のある馬を危険な存在として評価し、馬券の買い目から外す、あるいは評価を下げるという考え方です。特に、スタミナが絶対的に必要となる2200メートル以上の長距離レースにおいて、かかり癖を持つ馬が人気を集めている場合は、絶好の「消し」のチャンスとなります。ファンはその馬の持つ能力を評価して人気にしていますが、我々は「かかり癖」というデータに基づいた明確な不安要素を知っているため、他者よりも一歩進んだ判断ができるのです。同様に、メンバー構成から「スローペースが濃厚」と予測されるレースでも、かかり癖のある馬はストレスから暴走するリスクが高まるため、評価を下げるのが賢明です。
一方で、より攻撃的な戦略として、「チャンスに変える」という考え方もあります。例えば、かかり癖のある馬が、逆にその前向きな気性がプラスに働く可能性のある1600メートル以下の短距離・マイル戦に出てきた場合です。この距離であれば、たとえ多少かかったとしても、スタミナ切れを起こす前にゴールまでなだれ込める可能性があります。また、最も高度な戦略として、かかり癖のある馬を「展開の起爆剤」として利用する方法があります。例えば、「かかり癖のあるAという馬が、おそらくレース序盤で暴走し、ハイペースを作り出すだろう。その結果、Aを含む先行集団は後半に失速するはずだ。ならば、その展開の利を受ける後方待機のBという穴馬を狙ってみよう」という思考です。これは、かかっている馬そのものを買うのではなく、その馬が作り出す特殊なレース展開を予測し、そこから利益を得ようとする、非常に戦略的な馬券術です。このように、かかり癖というデータを深く読み解くことで、単に馬の能力を比較するだけの一次元的な予想から、レース全体の展開までをも見据えた、多角的で深みのある予想へと進化させることができるのです。
かかり癖は治る?トレーニングと騎手の調教法
多くの競馬ファンや馬券購入者を悩ませる馬の「かかり癖」。一度ついてしまったこの厄介な悪癖は、果たして治すことができるのでしょうか。これは、競走馬を管理する調教師や厩舎スタッフ、そしてレースで手綱を取る騎手にとって、常に付きまとう永遠のテーマの一つです。結論から申し上げると、かかり癖を100%完全に取り除くことは非常に困難な場合もありますが、陣営の根気強いトレーニングと、騎手の適切な調教法によって、その症状を大幅に改善させ、馬のパフォーマンスを向上させることは十分に可能です。それはまるで、多感な若者の個性を尊重しながら、社会性を身につけさせる教育のような、地道で奥深いプロセスなのです。
その理由として、馬の気性には血統などからくる先天的な要素がある一方で、後天的な経験や学習によって精神的な成長を促すことができる点が挙げられます。馬は非常に賢く、学習能力の高い動物です。そのため、トレーニングを通じて「レースでは興奮して暴走するのではなく、リラックスして走った方が楽であり、最終的に良い結果に繋がる」ということを、体と心で覚えさせることが改善の鍵となります。この「教育」の中心となるのが、日々の調教です。調教師や厩舎スタッフは、ただやみくもに馬を走らせて体力をつけるだけでなく、一頭一頭の気性や性格に合わせた、きめ細やかなトレーニングメニューを組み立てます。
その具体的な調教法の一つとして、最もポピュラーなのが「併せ馬」です。これは、二頭以上の馬を同時に走らせるトレーニングで、レース本番に近い状況を作り出すことができます。かかり癖のある馬に対しては、様々なバリエーションの併せ馬が試されます。例えば、あえて他の馬の後ろにつけさせ、前を「壁」にする練習を反復することで、馬群の中で我慢することを覚えさせます。逆に、他の馬を先行させて追いかける形を取り、闘争心を煽りすぎずに追走する訓練を積むこともあります。重要なのは、時計(タイム)を出すことだけが目的ではないということです。速いタイムを出すことよりも、いかにリラックスして、騎手の指示通りにスムーズに走れるかという「折り合い」の練習に重点が置かれます。この地道な反復練習によって、馬は他の馬が近くにいても冷静さを保つ術を少しずつ学んでいくのです。
また、馬具の工夫も、かかり癖の矯正において非常に重要な役割を果たします。騎手と馬との唯一の物理的な接点であるハミ(口にくわえる馬具)は、その形状や材質によって馬に与える影響が大きく異なります。かかりやすい馬に対しては、口当たりが柔らかいものや、舌を抑えることで騎手の指示が伝わりやすくなる特殊な形状のハミに変更するなど、試行錯誤が繰り返されます。さらに、視覚的な刺激をコントロールするために、シャドーロール(鼻面に装着し、自分の足元の影に驚かないようにする馬具)や、ブリンカー(目の横に装着し、後方や横の視界を遮って前方に集中させる馬具)といった矯正馬具が用いられることも少なくありません。どの馬具がその馬に合うかは個体差が大きく、陣営はまるでパズルのピースを組み合わせるように、最適な組み合わせを探し続けます。
そして、これらのトレーニングや馬具の工夫を最終的にレースで結実させるのが、騎手の役割です。特に、レースでの騎乗を予定している主戦騎手が、普段の調教からその馬に跨り、密なコミュニケーションを取ることは、かかり癖の改善に不可欠です。調教を通じて馬の癖や性格を肌で感じ取り、「どういう乗り方をすればこの馬はリラックスできるのか」「どのタイミングで合図を送ればスムーズに反応してくれるのか」といった、馬との「対話」の方法を探ります。この信頼関係が、レース本番での冷静な騎乗に繋がるのです。また、レースそのものを「教育の場」として利用することもあります。特に精神的に未熟な若駒の場合、目先の勝利にこだわらず、あえて馬群の中で我慢させる競馬を経験させ、「かからなくても最後までしっかり走れる」という成功体験を積ませることが、将来の大きな飛躍に繋がることがあります。このように、かかり癖の改善は、調教師の緻密なトレーニング計画、厩舎スタッフの日々のケア、馬具の専門的な選択、そして騎手の高度な技術と深い馬への理解、これらすべてが一体となったチームプレーの賜物なのです。一頭の馬が、悪癖を克服して大舞台で活躍する姿の裏には、こうした関係者たちの知られざる努力と愛情が込められていることを知ると、競馬観戦がより一層味わい深いものになるでしょう。
【比較表】かかりやすい馬 vs 折り合える馬の特徴
競馬というスポーツの奥深さは、単なるスピード競争ではなく、馬という繊細な生き物と人間との共同作業にあると言えます。その関係性の良好さ、あるいは不調和を最も端的に示す現象が、これまで解説してきた「かかる(折り合いを欠く)」状態と、その正反対である「折り合えている」状態です。この二つは、まさにコインの裏表、光と影のような対照的な関係にあります。結論として、これら二つのタイプの馬が示す特徴を比較し、その違いを明確に理解することは、レースの結果を予測し、より精度の高い馬券戦略を組み立てる上で、最強の武器となり得ます。ここでは、これまでの議論の総まとめとして、両者の特徴を項目別に徹底比較し、その違いがもたらす意味を深く掘り下げていきます。
1. 精神状態(パドック・返し馬での気配)
まず、レースが始まる前の気配、すなわち精神状態において、両者は明確な違いを見せます。
・かかりやすい馬:パドックの時点から、まるで戦場に向かう前の興奮しきった戦士のようです。発汗が激しく、特に首筋や股間から玉のような汗を流し、時にはそれが白く泡立っていることさえあります。歩様は落ち着きがなく、小刻みに足踏みをする「チャカチャカ」とした動きを見せ、厩務員の指示を無視して前に進もうとします。首を不自然に高く上げ、周囲を威嚇するように嘶いたり、他の馬に噛みつこうとしたりする姿は、有り余る闘争心が空回りしている証拠です。返し馬では、騎手が乗った瞬間に暴走気味に走り出し、必死に抑える騎手との綱引き状態が繰り広げられます。これらはすべて、内なるエネルギーをコントロールできていない危険なサインです。
・折り合える馬:一方、折り合える馬は、パドックでは適度な気合を内に秘めつつも、非常にリラックスしています。歩様はゆったりとして力強く、周囲の喧騒に動じることなく泰然自若とした態度を示します。発汗も穏やかで、心身ともに落ち着いていることが一目でわかります。返し馬では、騎手の指示に素直に従い、軽やかなキャンターで馬場を一周します。その姿は、これから始まる大一番に向けて、心と体の準備が万全に整っていることを示しており、観る者に絶対的な安心感を与えます。
2. 騎手との関係(レース中のコミュニケーション)
レース中の騎手との関係性ほど、両者の違いが顕著に表れるものはありません。
・かかりやすい馬:騎手との間に信頼関係はなく、あるのは抵抗と反発です。騎手が手綱で送る「待て」のサインに対し、首を激しく上下に振ったり、ハミを強く噛んで口を開く「口を割る」仕草を見せたりして、全身で抵抗の意思を示します。騎手はレース展開を考える余裕などなく、ただひたすらに馬をなだめ、抑えることに全神経を集中させなければなりません。これは人馬一体とは程遠い、不幸な不協和音の状態です。
・折り合える馬:騎手とは完璧なパートナーシップを築いています。手綱を通じて伝わる騎手の微細な意思を正確に感じ取り、まるでテレパシーで会話しているかのようにスムーズに反応します。騎手は馬を抑えることに余計な力を使う必要がないため、レース全体の流れを読み、ライバルの動きを見極め、最適なタイミングでスパートの指示を出すことに集中できます。これこそが、競馬の醍醐味である人馬一体のハーモニーです。
3. 走り方とスタミナ消費
走り方、そしてそれに伴うエネルギー効率も、両者は全く異なります。
・かかりやすい馬:その走りは力み返っており、非常に非効率的です。全身の筋肉が硬直し、呼吸も浅く乱れているため、無駄なエネルギーを大量に消費します。これはスタミナの源であるグリコーゲンをレース序盤で使い果たすことに繋がり、勝負どころである最後の直線に差し掛かる頃には、すでにガス欠状態に陥っています。マラソンで言えば、スタートから100m走のペースで突っ込んでいくようなもので、完走すらおぼつかない危険な走り方です。
・折り合える馬:その走りはリズミカルで滑らか、そしてエネルギー効率に優れています。リラックスして深い呼吸をしながら走ることで、有酸素運動を主体とした効率的なエネルギー消費を実現します。これにより、レース道中でのスタミナ消耗を最小限に抑え、勝負どころで爆発させるための脚(パワー)を温存することができます。これは、ペース配分を完璧にこなす熟練のマラソンランナーの走りに他なりません。
これらの比較から分かるように、「かかりやすい馬」と「折り合える馬」の違いは、単なる気性の問題ではなく、レースの勝敗そのものを決定づける根源的な要素です。競馬予想を行う際には、この比較表を頭の中に思い描き、出走馬一頭一頭がどちらのタイプに近いのかを、パドックの気配や過去のレースぶりから見極める作業が不可欠です。それは、不安定でリスクは高いが爆発力を秘めた投資対象と、安定していて信頼できるがリターンはそこそこの投資対象を見極める作業にも似ています。この物差しを手にすることで、あなたの競馬観戦と馬券戦略は、より深く、より論理的で、そして何よりもエキサイティングなものへと変わっていくことでしょう。
競馬の「かかる」とは?その全てを徹底解説【総まとめ】
記事をまとめます
競馬の「かかる」とは馬が過度に興奮し騎手の制御が効かない状態である
レース序盤での致命的なスタミナ消耗に繋がり大敗の主因となる
馬自身の気性、レースペース、騎手との相性などが複合的な原因だ
血統的に前向きすぎる気性を受け継いだ馬はかかりやすい傾向にある
「折り合い」は馬がリラックスし人馬一体となった理想の状態を指す
騎手が綱引きのように手綱を引く姿はかかる馬を抑えているサインだ
馬が首を激しく上下に振ったり口を割ったりするのは抵抗の証である
パドックでの多量の発汗や落ち着きのない歩様は危険な兆候だ
返し馬で騎手の制御を振り切って走る馬は本番でも要注意だ
騎手は他の馬を「壁」にしてかかりやすい馬をなだめる技術を持つ
かかり癖は併せ馬などの調教や馬具の工夫によって改善の可能性がある
長距離レースではかかる馬の評価を下げることが馬券戦略の基本となる
逆にかかる馬がハイペースを作り後方馬に展開が向くこともある
データや過去映像でかかり癖を把握することが予想精度を上げる鍵だ
かかる馬を見抜く力は危険な人気馬を避け高配当を掴む武器になる